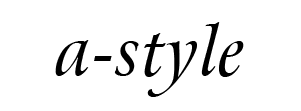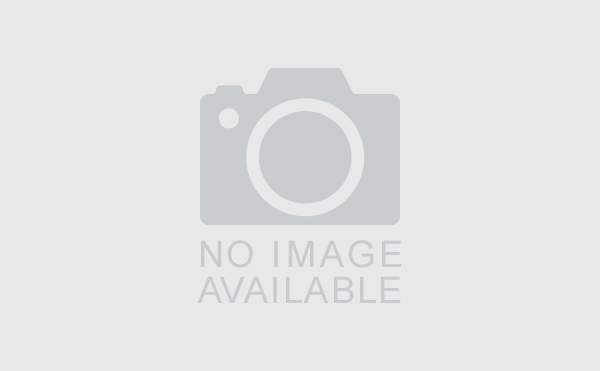『美と発酵』について😋
a-styleのブログをご覧頂き、ありがとうございます🙇💕
今日は🙌🏻
『美と発酵』〜発酵の基本Q&A〜について

発酵と聞くと、からだによさそうな気はするけれど、
実はよくわかっていないという人も多いのでは?
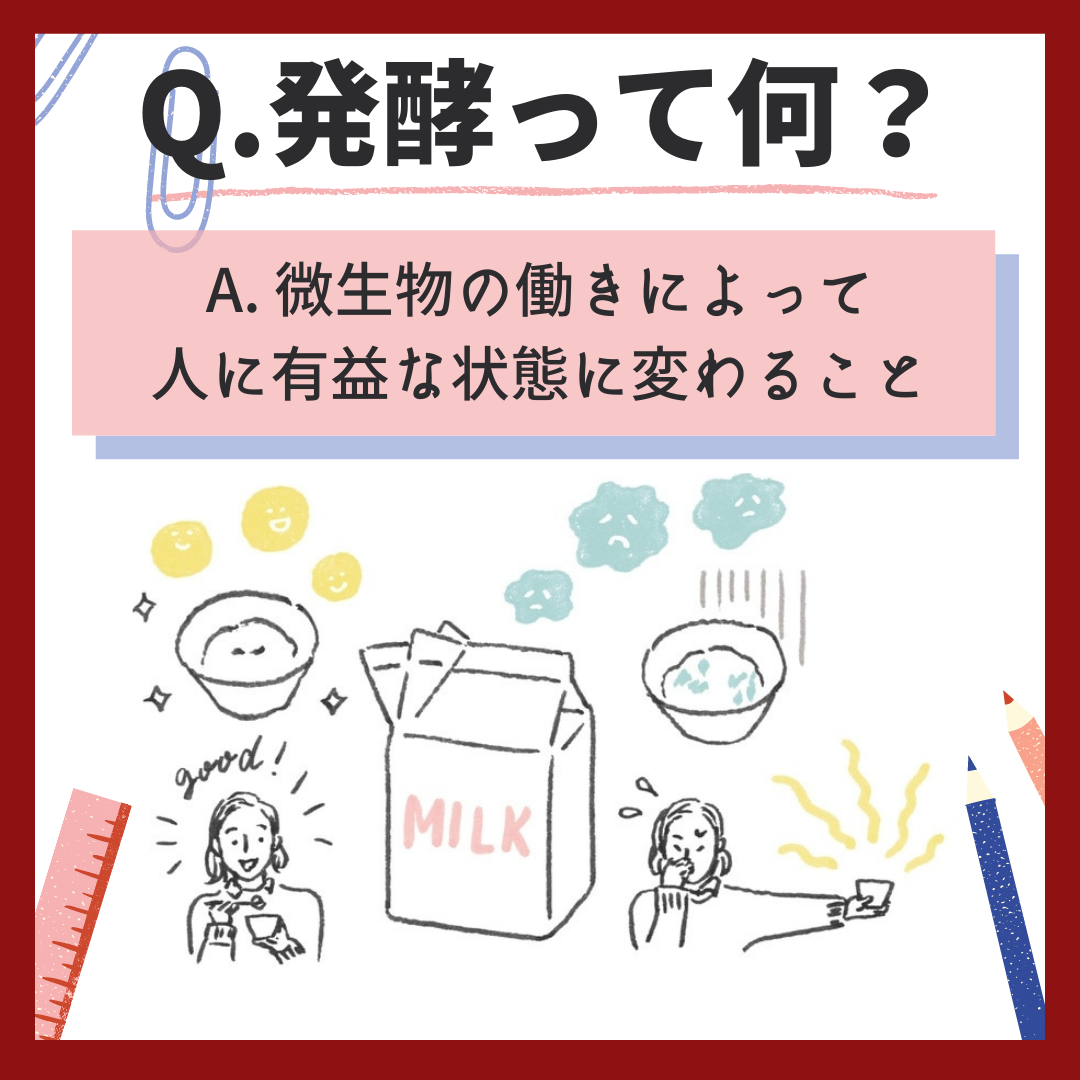
Q1.そもそも発酵って何?
A. 微生物の働きによって人に有益な状態に変わること
「発酵」とは、目に見えない微生物の力で食材を変化させ、おいしくなる、日もちする、栄養が増すなど、人にとってメリットのある状態にすること。反対に、微生物のせいで食材が人の害になる状態に変化するのが「腐敗」です。実は、この2つは同じメカニズムで、人間が「有益」と「有害」に仕分けしているだけ。長い歴史の中で、私たちは「発酵」したものを食品として摂るようになり、誰もが再現できるメソッドに磨き上げたのです。

Q2. 発酵食品にはどんな菌がかかわっているの?
A. 発酵食品を作る微生物は「細菌」「酵母」「カビ」の3 つ
微生物は大きく「細菌」「酵母」「カビ」の3種類に分かれます。細菌の代表的なものには、納豆菌、乳酸菌、酢酸菌などがあります。たとえば、大豆を蒸して柔らかくし、納豆菌をつけて発酵・熟成させたものが納豆です。酵母にはビール酵母や清酒酵母などアルコールを醸造する酵母菌、発酵させてパンを作るイースト菌などがあります。カビの代表は麹菌です。味噌、しょう油、かつお節、清酒などは、麹菌がかかわっています。
[微生物とそれらが生み出す食べ物例]
乳酸菌…チーズ、ヨーグルト、しょう油、漬物
納豆菌…納豆
酵母…パン、味噌、しょう油、清酒、ワイン、ビール
カビ…チーズ、味噌、しょう油、かつお節、清酒
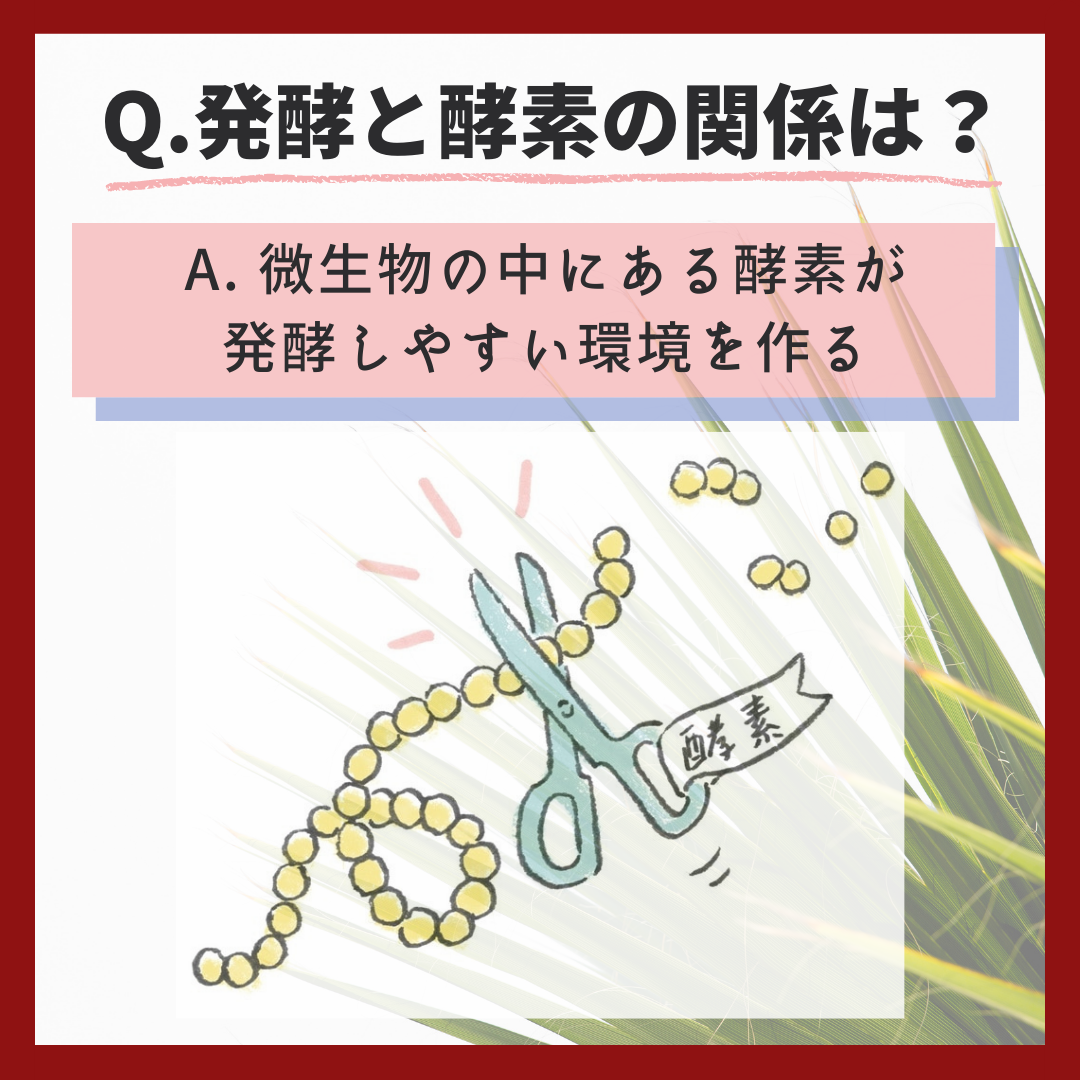
Q3. 発酵と酵素の関係は?
A. 微生物の中にある酵素が発酵しやすい環境を作る
「 酵素」はたんぱく質の一種。発酵による食品の変化は、微生物がもつ酵素によって起こります。たとえば、日本酒はお米を麹菌と酵母を使って発酵させたものですが、米はデンプン(=ブドウ糖が連結したもの)のままだと発酵しません。そこで、先に麹菌のもつ酵素の力でブドウ糖をバラバラにすることで、酵母が仕事をやりやすい環境を作るのです。たんぱく質をアミノ酸に分解する酵素もあり、それぞれ食品の甘みや旨みを引き出す働きもします。
次回は「発酵食品はなぜからだにいいの?」から説明します(^^♪